(これ書いてるのは7/11だけど)今日は勝鬘院の愛染まつりへ行ってきました。去年も来たけど。今年も盛況で。
ベビーカステラの(名前の)元祖の三宝屋が営業してたので買ってみました。なかなかおいしかったです。
写真は後日貼るかも。
(弱りゆく記憶力の補助)
(これ書いてるのは7/11だけど)今日は勝鬘院の愛染まつりへ行ってきました。去年も来たけど。今年も盛況で。
ベビーカステラの(名前の)元祖の三宝屋が営業してたので買ってみました。なかなかおいしかったです。
写真は後日貼るかも。
唐招提寺の前でタクシーに乗る。タクシーの運ちゃんも好きであっちこっち廻っているそうで移動中いろいろ話してくれました。
で、秋篠寺へ。年に今日6月6日だけ公開される大元帥明王(たいげんみょうおう)像を見るために来ました。
今年は1300年祭で11月に2週間ほど公開されるんだけど、その頃は他にもいろいろ見ないといけない気もするのでまとめて見てしまえってことで。
香水閣ってところにある井戸から湧く霊水と言われる水が飲めるようになっていたので1杯いただく。ここも普段は門が閉まっていて中に入ること自体も1年で今日だけなんだそうな。



特別な日だからかかなり人が多かったです。

で、近鉄を乗り継ぎ薬師寺へ。今年の終わり頃に8年の改修工事に入る国宝の東塔の初層が公開中ってことで。ま、秋まで公開中なので今日じゃなくても良かったのであるが、唐招提寺のついでで。
修学旅行生が大量にいてしゃれんらんほど人がいっぱいでした。凄すぎで、金堂と講堂は入らず。ま、何度も来てるしね。


ってことで、薬師寺の凄い人出に危機感を憶えながら500mほど北にある唐招提寺へ。
年にこの3日間だけ公開される御影堂に行ってきました。
去年修復が完了した金堂。ちゃんと見たのは初めてだな。ここもかなり人が多かったです。早めに来てたら洒落ならんくらいだったでしょうな。

ってことで特別公開中の御影堂(みえいどう)へ。西本願寺の御影堂は「ごえいどう」と言いますな。
3時くらいに行ったんだけど、待ち時間なしで入れました。が、それでも中は人でごった返し。
鑑真和上像は1年前に見たときは間近で見れましたが、まぁしゃあないですな。
東山魁夷の絵も去年見たけど、本来の場所で見る方がよいですな。

今年の6月6日は良い天気でしたな。
ってことで、今日も奈良へ。来週にしようかなとも考えたんだけどまとめて行ってしまえと言うことでまずは東塔西塔の初層が初公開中の當麻寺へ。



観光立国というならば観光地の電柱を無くすのを早くやって欲しいもんだと思う。
帰りに駅前の有名な店で中将餅を買いました。あんこに隠れていますが草餅です。最小構成の2個入りで。駅のベンチで食いました。やっぱ作りたてはめっちゃうまいですな。

ってことで、渡岸寺観音堂から6kmほど離れた己高閣(ここうかく)&世代閣(よしろかく)へチャリで向かいました。これが向かい風きついのなんの。めっちゃ疲れました。
途中、猿発見。めっちゃいっぱいいました。私を見て逃げていきましたが。


敷地は与志漏(よしろ)神社の境内にあって、同じ敷地には戸岩寺と言うお寺のお堂もあり、そのお堂の中を覗くともっと近くで見たいなと思わせる仏像が安置されてたり。
ってことで、今日の予定終了。5時までにチャリを返せと言われていたのですが、帰りは追い風だったので4時15分頃に出発したんだけど25分弱で戻れまして、4時44分発の電車に乗れました。
帰りはJRで。長浜から新快速とは言え2時間は疲れるな。
長浜から少し北のJR高月駅で降りました。渡岸寺観音堂の国宝の十一面観音像を見に。
スケジュールの関係で元々ここに来る予定はしてなかったんやけど、タクシー使えば行けるかなと思ってここに来ることにした。で、高月駅にレンタサイクル発見。借りました。そこでついでにどうぞと歴史民俗資料館の割引券をもらいました。
ってことでまずは歴史民俗資料館へ。渡岸寺観音堂のすぐ隣にあります。
建物は小さい2階建て。撮り損ねました。
この2体の仏像が初公開だそうな。かなり珍しい釈迦苦行像なんかも展示されていました。


本堂には観音様はいませんで、お隣の慈雲閣にいらっしゃいます。本堂は無料。


今日は会社を休んで湖北へ。
まずは竹生島(ちくぶしま)。実は先週ここに来損ねたのであった。
宝厳寺の千手観音が西国三十三所のご開帳キャンペーンでの開帳が30日までってことで。
本来の開帳は60年に1回だそうで、次は27年後だそうだ。
今日は先週より早めに家を出てJR長浜から長浜港へ。ここで船に乗り竹生島へ。


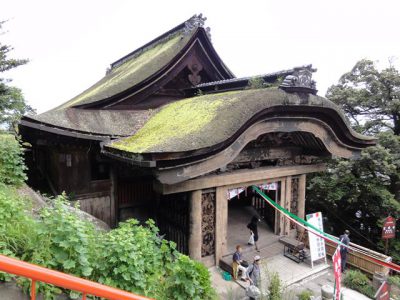
唐門の中には賓頭盧尊者像(びんづるさん)がいます。自分の体の悪いところと同じ場所を撫でると治ると言われる「なで仏」として結構どこのお寺にもいらっしゃいます。撫でられまくっているのでつるつるだったりしますが、びんづるさんを集めたサイトでも作りたいなと思ってしまう今日この頃ですが、写真に収めてないところも多いからなぁ。
今回特別開帳されていた観音様は厨子に入った状態で開帳されてるので全体は拝めずちょっと残念でした。
ま、でも貴重な機会なのでありがたくお参り。
重要文化財の船廊下(船底をひっくり返したような天井なんだそうで)と観音堂。上の写真の反対側から撮影。


こっちは本堂。弁天様をまつっています。こっちはほんとに60年に1回のご開帳だそうで、次は27年後。


ってことで、滞在時間が80分で帰りの船が出てしまいます。見所が結構あるので売店で飯食ったりする時間がありませんでした。1本遅らせることも可能なようだけど、次に行くところがあるので出発。
長浜駅の観光案内所にはフェリーの割引券が置いてありました。ま、先に来るのは不可能だからしゃあないな。
今日はここに来る予定ではなかった。まずは滋賀県某所へ向かうために大阪駅から新快速に乗ったのであるが、踏切で警報装置が押されたとかで20分以上遅れたので予定が完全に狂ってしまい、京都駅で降りた時点で滋賀に向かうのを諦めた。
ってことで、そのまま京都駅から近鉄で奈良へ向かった。東塔内部公開中の藥師寺に行こうかなと思ったんだけど、如意輪観音公開中の談山神社へ行くことにした。
大和八木で乗り換え、桜井で降りてバスを待つこと30分、15時5分発のバスに乗って約25分で到着。
ここは神仏習合の融合具合がかなり強い神社で、如意輪観音を納めたお堂があったり、十三重塔があったりします。雰囲気も神社とお寺が混ざった感じ。



ってことで、楓が多そうだったので談山神社へは紅葉の時期にでも来たいな。
当然その時には聖林寺とかもね。
高雄では他にはどこも寄らずサクッとバスに乗り、龍安寺へ行ってきました。
大学卒業前に来て以来だったのでほぼ20年ぶりか。
日本の庭園では世界一有名な石庭(方丈庭園)。えらい人で。やっぱりやたら外国人客が多い。しかし土曜になんか来るもんじゃないですな。20年前に来たときはたまたまタイミングが良くて一人で独占できた時間が少しあって静かにぼーっと眺められたんだけど。出る直前に団体のおばちゃん達が入ってきてたので当時は人が少なかったってことではないんだけどね。
次は高雄の神護寺の国宝の五大虚空蔵菩薩像が特別拝観ってことで行ってきました。
今までは事前に往復ハガキで申し込みだったのが今回から事前申し込み無しってことだそうな。
春と秋の3日間ずつってことで、春が5/13~15で秋は10/13~15と今日だけ休日なので今日行くことにした。(今年の日程はオフィシャルサイトhttp://www.jingoji.or.jp/でどうぞ)
無ければ葵祭をもっとじっくり見るつもりだったんだけどね。
市バスで北野白梅町に行き、そこからJRバスに乗り換え高雄へ。ここからだと400円。
やたら短期間の特別拝観なんだけど、人はめっちゃ少ない。紅葉では日本で有数の名所なんだけどねぇ。